50年近く生きてきた中で簿記について全くの未経験の私が、簿記3級に合格できた体験談を記します(2025年10月に受験)。
簿記3級の試験勉強の一例として読んで頂けたらと思います。
はじめに
老後2000万円問題がでてからというもの、老後が心配でたまりません!
いや、老後だけではなく、今の生活もこころもとない!
そんな不安な生活をおくる中、お金の対策をしなくては!といろいろ調べました。
インターネット上の動画やブログ、また本や雑誌など、観たり、読んだり、聞いたりしてきました。
そうして、家計の見直し、保険のこと、株式のこと、経済のこと、などなど勉強してきました。
勉強していくなかで、「全ての日本人はFP3級と簿記3級を勉強すべきである」という動画に出会いました。
「FP(ファイナンシャルプランナー)3級と簿記3級は、お金に関する知識や社会の仕組みについて、初心者が網羅的に学べる資格であり、たとえ試験は受けなくても勉強する価値がある!」という感じの内容でした。
FP3級と簿記3級については、以前にも興味が湧き、本を買ったり、YouTubeの動画を観たりしたことはありました。
ただ、本だけのときは、読んでいても頭に入ってこず、すぐに眠くなったり、意味がわからなくて頭が痛くなったりと、途中で勉強を辞めてしましました。
一方、動画は、とてもわかりやすい解説で理解することができたので、一通り観ました。が、受験するつもりはなかったので、聞き流して終わっていました。
<受験しようと思ったきっかけ>
私の場合は、シンプルに受験勉強するための時間ができたためです。 できた時間で、以前から興味のあったFP3級と簿記3級を勉強しよう。勉強するならば、成果がわかるように受験をしよう。と思ったためです。
試験は、先にFP3級を受験し、その後、簿記3級を受験しました。
【FP3級の体験談はこちらのページに記載しています】
※「はじめに」の文章は同じ内容です。
簿記3級試験の概要
・簿記3級試験は、日本商工会議所が主催する簿記検定、経理・会計の基礎知識を問うもので、試験概要は以下のようになっています。
詳しくは、日本商工会議所のHPへ(日商簿記検定試験(2級・3級)ネット試験について | 商工会議所の検定試験)。
〇試験方法はペーパー試験とネット試験があります。私はネット試験を受けました。
①試験形式:2種類
・統一試験(ペーパー試験)年3回
・ネット試験(CBT方式)随時受験可能
※ネット試験は、事前に予約した試験会場で、パソコンを使用して受けます。
②試験時間 :ネット試験・筆記試験ともに60分間
③問題構成:
・第1問:仕訳問題(15問、配点45点)
・第2問:語句記入・補助簿選択・勘定記入(配点20点)
・第3問:決算書作成問題(配点35点)
④合格基準: 100点満点中70点以上で合格
⑤受験資格 :特に無し(誰でも受験可能)
⑥合格率 :ペーパー試験で約36%、ネット試験で約40%程度。
全体では30~50%程度で推移。
⑦勉強時間 :合格に必要な勉強時間の目安は約50~120時間
※簿記3級を取得するメリット
・会社の経営状況を判断できるようになる、
・確定申告や会計処理がスムーズになる
・上位資格(簿記2級、税理士、公認会計士など)の学習に役立つ
など
簿記3級の勉強内容
①試験日までの勉強の流れ
勉強は、YouTubeにアップされている「ふくしままさゆき」さんの動画視聴をメインに行いました。
(【簿記系YouTuber?】ふくしままさゆき – YouTube)
動画は、簿記について知識が全く無い私にも理解できるようにわかりやすく解説されていました。
ただ、簿記という慣れない世界の壁は高く、簿記で使われる用語、考え方はすぐには身につきませんでした。
最初、動画を1周見終わった時に解いた総復習問題70問(やさしめ)では3分の1も正解できず、散々な結果でした(T_T)
とはいえ25本ある動画を3週、4週していくうちに、簿記について理解が深まっているのがわかりました。
動画3週目が終わると、なんとなく簿記の全体像がつかめたので、本番試験はどのようなものかを知るために、CPAラーニングの解説動画を見て、模擬試験(ネット試験)を解いてみました。
(CPAラーニング|簿記や会計を完全無料で学ぶならCPAラーニング)
動画4週目が終わると、かなり理解できているのが分かったので、模擬試験と練習問題を何度も解いて、間違いやすい部分の確認や理解不足の部分の見直しを行いました。
このころには、合格ラインは超えることができていました。
ただ、何度やっても、ちょっとしたミスで不正解の部分がでてしまっていました。 そのため、ミスのないようにと、試験当日までできる限り何度も問題を解きました。
②動画の再生速度
動画視聴は、回を重ねるごとに再生速度を早くしていきました。
1~2週目は1.5倍速、3週目は1.75倍足、4週目は2倍速。
動画を見る時間が短くなって、勉強時間の短縮にもなりました。
はじめは早くすると聞き取れない部分がありましたが、何度も聞いていると早くしても聞き取れるようになっていました。
また、動画を見ながら、ポイントと思うところや忘れがちなところをノートに書いて、ノートを見ながら動画を見ていました。
③本番試験対策
試験は、紙によるペーパー試験とネット試験の2種類があり、私はネット試験で受験しました。
ネット試験については、上文にも記載しましたが、CPAラーニングという「簿記や会計を完全無料で学べるeラーニングプラットフォーム」をインターネットで見つけられたので、こちらを利用しました。
(CPAラーニング|簿記や会計を完全無料で学ぶならCPAラーニング)
CPAラーニングは無料なうえに、簿記以外にも会計関係の資格試験に対応していました。
私は、本番のネット試験と同じように受けられる模擬試験とその対策動画を利用しました。
なんと、CPAラーニングの中には、「ふくやままさはる」さんの動画も入っていました。
④勉強時間
試験日までの勉強時間は、1日1~2時間程度、たまに3~4時間行いました。
トータルでは85時間でした。
勉強した日数は54日で約2か月かかりました。
試験日は自分で決められましたが、ある程度理解できた後に、受験申し込みを行ったので、勉強時間としては妥当だったと思います。
簿記3級の一般的な勉強時間は、50~120時間、ゆっくり目で100時間と言われています。
私の勉強時間は平均くらいなのかなと思いました。
受験
①受験開始前
FP3級の受験時と同じ会場で受けたので、初めての時よりは慣れた感じで受付が行えました.
受け付けでは、名前を伝えて、試験の確認(他の試験も実施していました)、身分証の確認、顔の確認、用紙の記載事項の確認と名前等の記入をして、荷物をロッカーに入れ、時間まで椅子に座って待機し、係の方が試験の説明した後、試験会場に入り、自分の受験するパソコン(番号が書いてある)に座りました。
パソコンへ手順にしたがって必要事項を入力し、試験を開始しました。
②試験本番
試験がスタートすると、画面下に残り時間が表示され、1秒ずつ時間が減っていきました。
時間の表示や画面の表示内容、打ち込み方等、模擬試験と同じでした。
問題は、練習と違うと感じるものもあったので、思ったより悩みながら解いていきました。
模擬試験では、数字の入力ミスもあったことから、数字の入力時には何度か数字を見直たりと注意しながら、回答を進めていきました.
時間内に最後まで解けましたが、残り時間5分だったので、見直しはあまりできませんでした。時間になり、試験終了のボタンを押すと、すぐに点数と結果がでました。
結果は、85点の「合格」でした。
いくつかの問題はあっているか自信がなかったので、合格できてホッとしました。
感想
本番の試験では、模擬試験のときよりも焦りがでてしまい、問題を解きながら合格点がとれているのか不安になってしまいました。
また、今までの人生で、こんなにも数字ばかりを記入する試験がなかったことも、焦った原因だと思いました。
何度も同じ勉強を繰り返すことで、簿記を多少なりとも理解できて、簿記3級に合格できましたが、簿記(帳簿記入や決算整理)に慣れるのはまだまだ時間がかかると感じました。
とはいえ、簿記3級を受験した目的は、簿記の知識を得るためだったので、上位試験は受けないつもりです。
簿記を学んだことで、経理がどのように会計を処理していたのかや、社会経済の仕組みなど、今まで知らなかったこともたくさん知ることができて、とても有意義な時間でした。
次は、FP2級に挑戦したいと思います!
おまけ
もしも次受験する誰かにアドバイスするとしたら、以下のように伝えたいと思います。
①勉強は体系的に覚える必要がある。
一カ所をわかったつもりでも、他の項目(特に決算)では、忘れていることがありました。何度も繰り返し学ぶことで、関連づけて覚えられるようになっていきました。
②勘定科目を覚えることと、その勘定科目が5つの要素(資産・負債・純資産・費用・収益)のどれに当たるのかを覚えることは、必須事項。
これも、何度も繰り返し学ぶことで身についていきました。
③動画を1~2週したら、1度本番試験の解説動画も見ておくと良い。
なんとなく簿記についてわかったあたりで、本番の試験がどのような感じか見ておくと、勉強のやり方がわかってくると思います。
<試験本番の対策として>
④本番の試験は、パソコン上で解答していくため、事前の練習が必須(模擬試験など)。
試験時間は限られているので、あせって時間を消費することがないように事前に練習しておいたほうが良いと思いました。
⑤メモ書の方法を決めておくとよい。
パソコンへの回答のため、メモをする用紙とボールペンが用意されています。
解説動画でも言っていましたが、時間のない中で、メモをとるので、省略した書き方などができるとよいと思いました。
例えば)「売掛金」⇒「売×」、「10,000」⇒「10,-」など。
余談:私は、単位を漢字にしてメモしました[100万とか]。単位を記載した方が、金額がわかりやすく、逆に数字のみだと間違えそうだったので。日頃1000単位で区切る数字になじみがなかったためだと思います。
⑥数字の入力ミスに注意する。
数字は、数字キーを自分で入力するので、ゼロの数を間違えないように意識したほうが良いと思います。模擬試験では入力試験を何度かやってしまいました(>_<)。
⑦勘定科目は少々曖昧でも大丈夫なこともある。
勘定科目を覚えることは必須ですが、試験では勘定科目を選ぶようになっているものが多いので(スクロール形式)、少々曖昧でも大丈夫な場合があると思います。
(完璧に単語を覚えていないとダメ!ということはないといいたいだけです。)
なお、第2問と第3問は、文字を打ち込む部分がありました。
⑧第2問、第3問は、全てを解けなくても(たとえ空白があっても)、部分点がもらえるため、できる限り書き込みましょう。
以上、あくまで個人的な見解ですが、参考になればうれしいです。
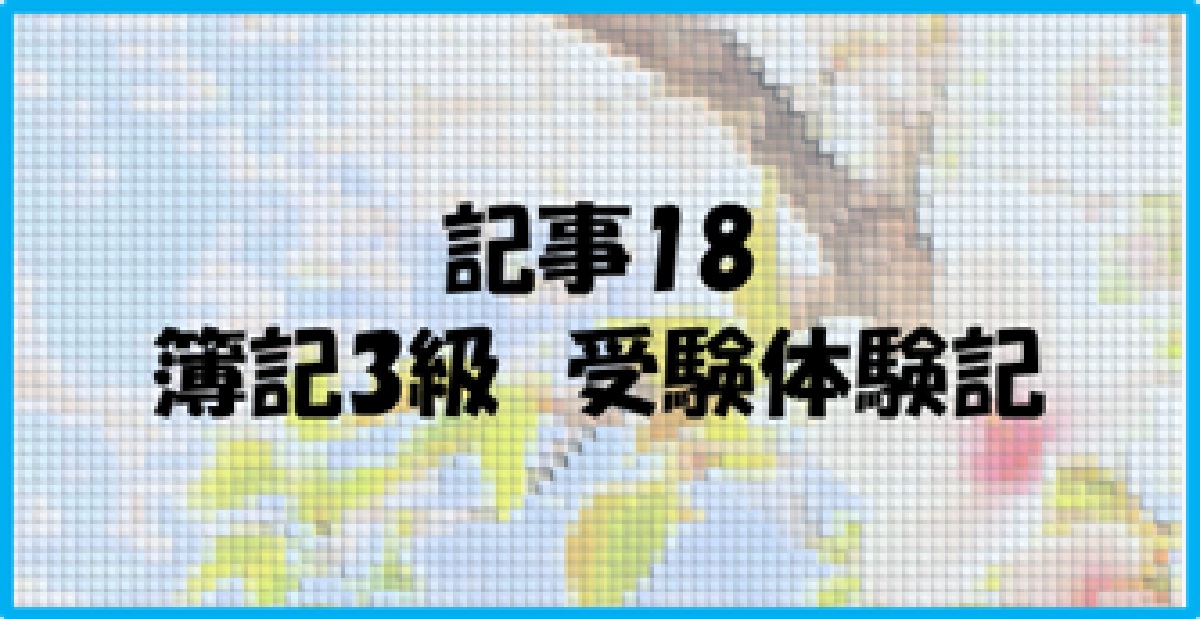
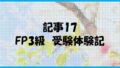

コメント